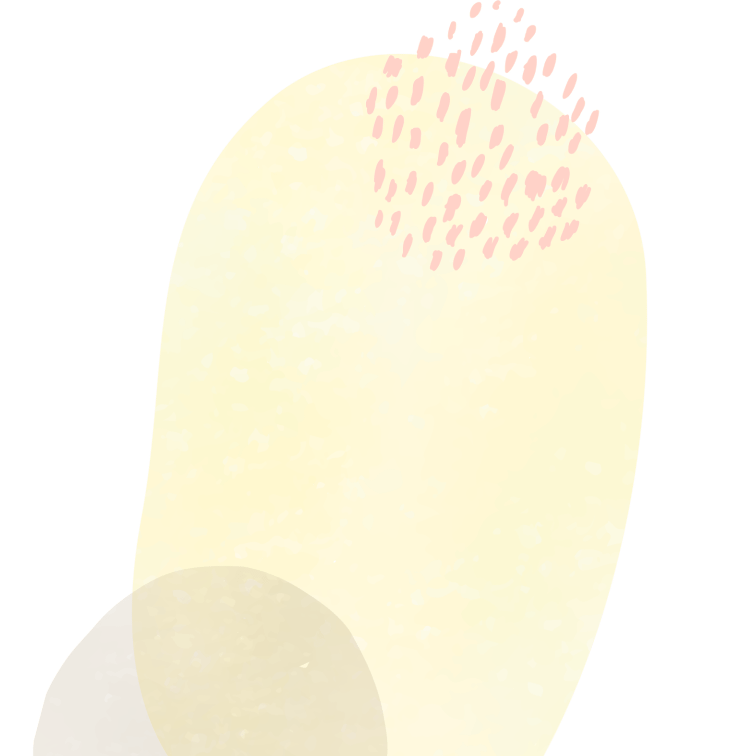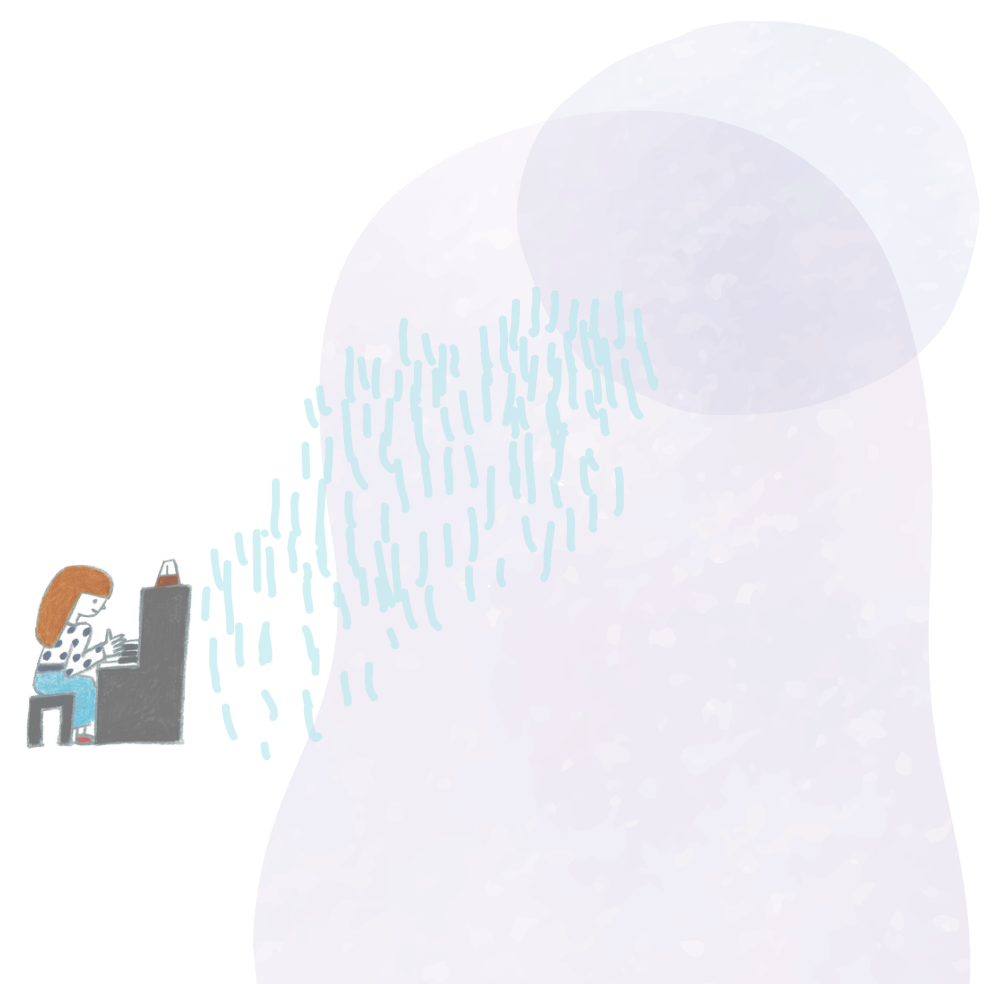壁に描けば落書き、紙に描けばお絵描き
私は保育士としてカナダで5年半ほど勤めていました。そこでの大きな学びは、子どもたちの一見「問題」に見える行動も、実はその子なりの大切な「表現」だということ。その学びを活かし、まずはありのままを受け入れることから私の支援は始まります。例えば、白い壁があると落書きをしたくてしょうがない子の場合。壁が落書きだらけになり、普通なら「やめなさい」と止めるかもしれません。しかし、私たちは、壁紙を新しく貼り直すのではなく、あえて大きな紙を貼ることで、「落書き」を「お絵描き」に変えました。またトイレの壁紙を破いて流してしまう子の場合は、あえて壁紙を全部剥がし、一緒に他の「表現」方法を探しました。世間的に見栄えは悪いかもしれません。でも、きれいに見せることより、子どもたちが生活しやすいかどうかの方がずっと大切だと思っています。その子の表現したい気持ちを否定するのではなく、より良い方向に導く環境を整えることも私たちの仕事です。

個性を大切にしながらも、社会で生きるルールは伝える
一方で、個性を大切にするということは、何でも受け入れればいいということではありません。「障害だから仕方ない」と許容するだけではなく、その子がわかる範囲できちんと社会のルールを伝える必要があります。例えば、お絵描きを例に取ると、「決まったところで書くのはOK、そうじゃないところはダメ」と伝えます。必ずしもできるとは限りませんが、子どもたちもいつか社会人になる。社会にはルールがあり、それを守らないと受け入れられないこともある。下手をすると、ちゃんとした教育を受けていないことで犯罪に巻き込まれる可能性があることを忘れてはいけません。そしてルールを伝える際は単に「ダメ」と言うのではなく、なぜそのルールが必要なのか、自分の未来にどうつながるのかを一緒に考えるようにします。障害があるから何をしても許されるというのは優しさではなく甘やかしであり、結果的にその子のためになりません。一人ひとりの子どもたちが、自分らしさを大切にしながらも、社会の中で幸せに生きていける。そんな支援を私たちは目指しています。